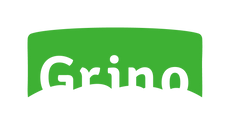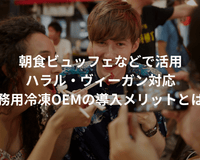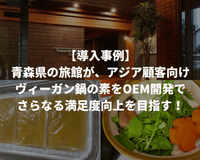自社ブランドの食品をOEMで製造したいと考えても、「どのように仕入れを進ればよいのか」「原材料や包装資材はどこまで自社で用意すべきか」など、悩む方は多いのではないでしょうか。食品OEMは、自社で工場を持ずに商品を生産できる効率的な方法ですが、仕入れの流れを誤るとコスト増や品質トラブルの原因にもなります。
この記事では、食品OEMの仕入れ方法や発注までの流れ、コストを抑える工夫やメーカー選びのポイントをわかりやすく解説します。初めてOEMを導入する方や、これから自社商品の生産体制を整えたい方は参考にしてください。
食品OEMとは?仕入れを始める前に押さえたい基本

食品OEM(Original Equipment Manufacturing)は、他社が企画した製品を自社ブランドとして製造する仕組みを指します。食品業界では、自社で製造設備を持ずに商品を展開できるため、初期投資を抑えながら新商品の開発が進められます。
ただし、仕入れ段階で仕様や数量を誤るとコストが膨らんだり、在庫過多に陥ったりするおそれがあるため、全体の流れを理解しておくことが欠かせません。
OEMとODMの違いを理解する
OEMは、依頼する企業が商品仕様を決めて製造を委託する方法で、ブランドの方向性や味・デザインを自社でコントロールできます。一方のODM(Original Design Manufacturing)は、メーカーが企画から設計までを担い、完成品を依頼企業のブランド名で販売する形です。OEMは「自社ブランドの再現性を重視する場合」、ODMは「専門メーカーの企画力を活かしたい場合」に適しています。
たとえば、自社レシピの再現や限定素材を使用したい場合はOEMが向きます。逆に、製品の経験や開発体制を重視したいときはODMを選ぶことで効率的な商品開発が可能になります。どちらを選ぶかは、ブランド戦略と社内リソースのバランスによって判断するのが理想的です。
食品OEMが活用される主な理由とメリット
食品OEMの導入が進んでいる背景には、コスト削減とスピード感の両立があります。自社で製造設備を持つ必要がないため、設備投資や人件費の負担を抑えつつ、短期間で商品を市場に投入できます。また、食品OEMメーカーは衛生基準を満した専用設備を備えており、安定した品質を維持しながら大量生産が可能です。
さらに、経験豊富なメーカーほどレシピ提案や改善サポートを行ってくれることもあり、自社だけでは難しい技術を取り入れられます。これにより、コストを抑えながらもブランド価値を高められるのがOEMの大きな魅力です。近年では、地域特産品や健康志向の商品開発など、企画の柔軟性を求めてOEMを採用するケースも増えています。
仕入れを始める前に確認しておきたい準備事項
OEMを始める際は、メーカーと話す前に社内で整理しておくことが大切です。特に、商品コンセプトや販売チャネル、ターゲット層を明確にしておくと、試作や見積もりの段階で齟齬が起きにくくなります。
-
販売数量の見込み(初回発注数・年間計画)
-
希望単価や原価構成(利益率を含めた試算)
-
パッケージやデザインの方向性
-
保存方法・賞味期限など品質条件
これらを準備しておくことで、OEMメーカーとの打ち合わせがスムーズに進みます。
また、原材料や容器の指定がある場合は、その根拠を明確に示すと相手側の理解が得やすくなります。最初の設計段階で丁寧に共有することが、コストや納期の最適化につながります。
食品OEMの仕入れ方法と全体の流れ

食品OEMでの仕入れは、企画から納品までの流れを理解することが大切です。工程ごとに意識すべきポイントを整理しておくと、取引がスムーズになりトラブルの防止にもつながります。
一般的な流れは以下のようになります。
-
商品コンセプトとターゲットを明確にする
-
見積もり依頼から試作・調整までを進める
-
発注から納品・検品・支払いまでを管理する
これらを順に進めることで、初めてOEMを導入する企業でも安心して取引を進められます。
それぞれの項目について、順番に詳しく解説していきます。
商品コンセプトとターゲットの明確化
仕入れの最初のステップは、「どんな商品を誰に届けたいか」を明確にすることです。販売チャネル(ネット販売・小売・業務用など)や顧客層を設定すると、求められる味・価格帯・パッケージが自然と見えてきます。例えば、若年層向けならデザイン性や話題性を重視し、高齢層向けなら栄養価や安全性を優先するなど、方向性を具体化することが大切です。
この段階でコンセプトが固まっていれば、OEMメーカーへの依頼も的確に行えます。結果として、試作段階での修正回数を減らせるため、コストと時間の両方を抑えられます。
見積もり依頼から試作・調整までのステップ
コンセプトが定まったら、複数のOEMメーカーに見積もりを依頼します。見積もり時には、希望ロット数や希望単価、パッケージ仕様、賞味期限などをできるだけ具体的に伝えることが重要です。メーカーによって得意分野や原料調達ルートが異なるため、提案内容を比較すると費用と品質のバランスが見えてきます。
見積もり後は試作を依頼し、味や食感、保存性、包装デザインを確認します。気になる点はその場で修正依頼を行い、納得できる品質を確保しましょう。試作の段階で十分にすり合わせを行うことで、量産後のトラブルを防ぐことにつながります。
発注から納品・検品・支払いまでの流れ
試作が完了し仕様が固まったら、正式な発注契約を結びます。契約書には製造数量、納期、支払条件を明記し、双方の責任範囲を明確にしておくことが大切です。製造中は進捗を定期的に確認し、納期に影響が出ないよう調整を行います。
納品時には品質・数量・包装状態をチェックし、問題があれば早めにメーカーへ報告します。初回取引では特に慎重な検品を行うことで、次回以降の信頼関係にもつながります。支払いは契約条件に沿って正確に行い、誠実な対応を続けることで、安定した取引基盤を築けます。
原材料・資材の仕入れとコスト最適化のポイント

食品OEMでは、原材料や包装資材の仕入れ方がコストに直結します。メーカーが一括手配する場合と、自社で指定・支給する場合の2パターンがあるため、どちらを選ぶかを明確にしておくことが重要です。
契約段階で役割を整理することで、無駄なコストや認識違いを防げます。
メーカー手配と自社手配の違いを理解する
メーカー手配では、仕入れや在庫管理を一任できるため手間がかからず、安定供給を実現しやすくなります。一方、自社手配では原料の品質を厳密に管理でき、独自素材を活かした商品づくりが可能になります。ただし、保管や輸送など追加コストが発生することもあるため、商品特性と生産規模に合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。
コストを抑えるための契約・ロット調整の工夫
コスト最適化には、製造ロットや契約条件の見直しが欠かせません。発注量を増やせば単価を下げられますが、在庫リスクが伴います。まずは小ロットでスタートし、販売実績に応じて発注を増やす方法が現実的です。また、長期契約を結ぶことで単価を安定させることもできます。複数商品の原料をまとめて仕入れる「共同仕入れ」も有効な手段です。
安定供給を実現する在庫・輸送管理のポイント
OEMでは、原料の確保や物流体制の整備も品質維持に欠かせません。製造スケジュールに余裕を持たせ、原料不足や輸送遅延を防ぐことが重要です。特に冷凍・生鮮原料は温度管理が品質に直結するため、輸送業者との連携を強化しましょう。安定した納品体制を構築することで、信頼されるサプライチェーンを築けます。
食品OEMメーカーを選ぶ際のポイント
メーカー選びは、OEMの成否を大きく左右する要素です。信頼できるパートナーを選ぶことで、品質とコストの両立が可能になります。比較検討の際は、実績・衛生基準・担当者対応の3点を軸に評価すると判断しやすくなります。
製造実績と得意分野を確認する
まず注目すべきは、メーカーの得意分野と実績です。調味料、惣菜、スイーツなど、ジャンルによって設備やノウハウが異なります。自社商品の方向性に近い実績を持つメーカーを選ぶことで、スムーズな製造と安定した品質につながります。類似商品の実績が多いメーカーほど、仕入れルートも確立している傾向があります。
品質基準・衛生管理体制をチェックする
食品製造では、衛生基準の高さが信頼性を左右します。HACCPやISO9001などの認証取得状況を確認し、検査体制や記録管理が整っているかを確認しましょう。見学が可能であれば、実際に工場を訪問して作業環境を確認するのがおすすめです。異物混入や温度管理のルールが明確なメーカーは、長期的に安心して取引できます。
担当者との連携力・対応力を見極める
OEM取引では、担当者の対応力も大切な判断基準です。問い合わせに対するレスポンスの早さや、改善提案の柔軟性を確認しましょう。誠実な対応をしてくれる担当者とは、トラブル時にもスムーズに解決できます。メーカーを“仕入れ先”ではなく、“共同開発パートナー”として関係を築く意識が重要です。
よくあるトラブルと防止策
OEMの仕入れでは、品質不一致や納期遅延などのトラブルが発生することがあります。これらは事前の取り決めと書面化で多くを防ぐことが可能です。契約段階で曖昧な部分を残さないことが安定取引への近道です。
品質不一致・納期遅延の原因と対処法
トラブルの多くは、仕様やスケジュールの共有不足が原因です。レシピや原料指定を口頭で伝えるのではなく、必ず書面にまとめて確認します。納期遅延を防ぐには、製造計画を余裕を持って設定し、進行状況をこまめに共有すると効果的です。問題が発生した場合は、双方で原因を振り返り、再発防止策を文書化しておくと信頼関係を維持できます。
契約書や仕様書で明確にしておくべき項目
契約書には、次の項目を明記しておくことが基本です。
-
製造数量・納期・支払条件
-
品質基準・検品方法・不良品対応
-
レシピ・配合比・原材料の扱い
-
知的財産・商標権の取り扱い
これらを明確にすることで、責任範囲をはっきりさせ、トラブル時の対応がスムーズになります。特に不良品対応と支払い条件は、事前に確認しておくことが欠かせません。
トラブル発生時の連絡・対応ルールを決める
トラブルが発生した場合の対応フローを決めておくと安心です。連絡経路や報告期限をあらかじめ設定し、情報共有を迅速に行える体制を整えましょう。また、発生原因と対応結果を記録に残すことで、次回以降の防止策にもつながります。こうした体制づくりが、長期的な信頼関係を育む基盤となります。
成功する食品OEM仕入れの進め方
OEM仕入れの成功には、短期的なコスト削減だけでなく、長期的な協力体制の構築が欠かせません。メーカーと互いの強みを理解し合い、信頼関係を築くことが継続的な品質維持につながります。発注から納品までの流れを可視化することで、安定した生産が実現します。
スケジュール管理と段階的な発注がポイントになる
スケジュールを明確にし、年間の販売計画をもとに発注時期を決めると、安定した製造体制を維持できます。小ロットで試験的に生産を行い、売れ行きを確認してから増産するのも有効です。需要変動や原料高騰にも対応できるよう、メーカーと情報共有を密にしておくと、柔軟な調整がしやすくなります。
小ロットから始めて信頼関係を築く
初回取引では、小ロットから始めて実績を重ねていくのが安心です。販売結果を分析し、改良を加えることでより高品質な商品へと成長します。メーカーとの信頼関係は、誠実な対応と安定した取引を通して築かれます。信頼を積み重ねることで、提案や協力が得やすくなり、より強いパートナーシップへと発展します。
まとめ|食品OEMの仕入れを成功させるために
食品OEMの仕入れは、単なる製造依頼ではなく、商品づくりの基盤となる大切な工程です。企画から原料調達、メーカー選定、契約までの各段階を丁寧に進めることで、品質とコストのバランスを保てます。特に、書面での確認や担当者間の連携を意識することが信頼構築の第一歩になります。
仕入れ方法を正しく理解し、長期的なパートナーとしてメーカーと協力することで、自社ブランドを安定的に育てていくことができます。OEMを活用して新たな商品開発を目指す方は、今回紹介したポイントを参考に、自社に合った仕入れの形を見つけてください。