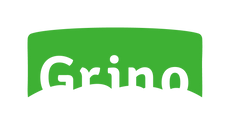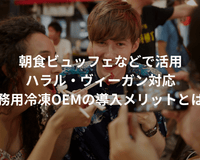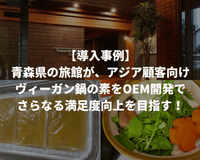時給1700円時代は目前?その背景と対策
近年、日本の労働市場では顕著な変化が起きています。特に注目すべきは、三大都市圏の外食業アルバイトの平均時給が2024年12月時点で過去最高の1187円を記録したことです。この上昇傾向は一時的なものではなく、構造的な要因によって今後も継続すると予測されています。本稿では、時給上昇の背景と今後の見通し、そして宿泊飲食業界が取るべき対策について考察します。
時給上昇の主要因
1. 深刻化する人手不足
日本の労働市場は完全な「売り手市場」となっています。少子高齢化による生産年齢人口の減少、若年層の職業選択の多様化などにより、特にサービス業界では人材確保が困難になっています。企業間での人材獲得競争が激化し、より高い時給を提示することが人材確保の必須条件となっています。人手不足倒産の事例なども!
2. 政府の賃金引き上げ政策
政府は2030年までに最低賃金の全国平均を1500円にする方針を打ち出しています。この政策目標を達成するためには、毎年着実な最低賃金の引き上げが必要となります。実際、過去数年間の最低賃金の上昇率は加速しており、この傾向は今後も続くでしょう。
3. 民間企業の賃上げ連鎖
2024年度、多くの大手外食チェーンが5%以上の賃上げを実施しました。この動きは中小企業にも波及し、業界全体で年率6~8%の賃金上昇が見込まれています。さらに、インフレ圧力も賃金上昇を後押ししています。

2030年の時給予測
現在の時給上昇率が継続すると仮定した場合、2030年までの時給予測は以下のようになります:
- 2024年:1187円(現状)
- 2026年:約1340円~1390円
- 2028年:約1510円~1620円
- 2030年:約1700円~1750円
この予測は一見すると急激な上昇に思えますが、現在の経済状況や政策動向を考慮すれば、十分に現実的なシナリオと言えるでしょう。
時給上昇がもたらす業界への影響
大手と中小の格差拡大
大手チェーンは資本力を活かし、清掃ロボットや配膳ロボット、セントラルキッチンなどの効率化投資を進めています。一方で、中小店舗では投資余力が限られており、人件費高騰の影響をより強く受けることになります。その結果、大手と中小の間の時給格差や経営体力の差はさらに拡大する可能性があります。
経営モデルの変革
時給の上昇は単なるコスト増加ではなく、飲食業界全体のビジネスモデルを変革する契機となっています。従来の労働集約型モデルから、効率性と付加価値を重視したモデルへの転換が求められています。
時給1700円時代に向けた対策
1. 業務効率化と省力化
バックオフィス業務のデジタル化や、作業工程の見直しによる効率化が不可欠です。顧客対応や調理プロセスを分析し、無駄な工程を削減することで、少ない人員でも質の高いサービスを提供できる体制を構築しましょう。
2. テクノロジーの活用
セルフオーダーシステムやキッチン自動化機器など、テクノロジーを積極的に導入することで人件費の抑制が可能になります。初期投資は必要ですが、長期的には大きなコスト削減につながります。
3. 調理済み食品の活用
完全調理済み冷凍食品などを活用することで、調理工程を簡略化し、熟練したスキルを持たない従業員でも一定品質の料理を提供できるようになります。これにより、人件費の上昇圧力を緩和できるだけでなく、メニューの安定性も確保できます。
具体的な対策事例はこちら!

まとめ
時給の上昇は避けられない現実となっています。しかし、この変化を脅威としてだけでなく、ビジネスモデルを見直し、より効率的で持続可能な経営への転換点として捉えることが重要です。早期に対策を講じ、変化に適応できる企業だけが生き残る厳しい時代が到来しています。
業務効率化や自動化、調理済み食品の活用など、さまざまな選択肢を検討し、自社に最適な解決策を見つけることが、時給1700円時代を勝ち抜くための鍵となるでしょう。
Grinoでは時短とインバウンド対策用に調理済みのユニバーサルレシピOEMに取り組んでいます。ご興味をお持ちいただけたらいつでもお気軽にご連絡ください。