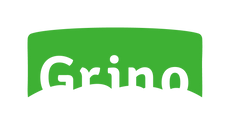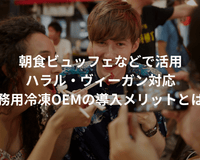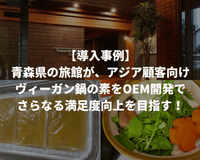はじめに
日本政府は2030年までに年間訪日外国人旅行者数6000万人、消費額15兆円という野心的な目標を掲げています。私たちGrinoはこの日本政府の目標や、私たち自身の予測もあり、近い将来やってくると考える未来像に向けて、必要な準備をする支援をしています。
ですが、この目標値は2023年比で訪日客数を約2.4倍、消費額を約2.8倍に増やす計算であり、現在の実績(2024年は約3,687万人・8.1兆円)を大幅に上回る非常に野心的な目標であることは間違いありません。そこで以下では、一度冷静にこの目標の達成可能性を検証した上で、この目標達成のために必要な条件と戦略を5つの観点から分析します。

1. 日本の観光受け入れ体制:経済・政策・インフラ・企業・リスク
産業の地位: 世界的なインフレや金融政策の影響で近年の円安傾向は訪日旅行を魅力的にしています。19年末から円は対ドルで約44%も減価し、実効為替レートでも26%下落したため、日本は国際観光市場で「格安」な目的地となりました。(一方、円安は関係ないという論もあります)例えば、日本のビッグマック価格は米国の約4割という水準で、訪日客の購買力は大きく増しています。この結果、観光業は日本の輸出産業として自然に成長しており、半導体や鉄鋼を上回る外貨獲得源となっています。この価格競争力は当面の追い風ですが、為替は変動要因であるため中長期的にはサービス価値の向上が必要です。
ビザ政策と入国制度: 観光需要拡大に合わせ、日本はビザ緩和や電子ビザ導入を進めています。中国やインドなど一部の国ではオンラインで申請できる電子ビザ制度が開始され、訪日前手続きの簡素化が図られています。また、タイやマレーシア等に対するビザ免除措置(2013年~)は東南アジアからの観光客増加に貢献しています。将来的にインドや中東諸国へのビザ要件緩和や電子渡航認証システムの導入も検討されており、円滑な入国管理とセキュリティ強化の両立が課題です。さらに入国審査の高速化も重要で、条件付きで大幅に簡素化できれば「週末旅行で気軽に来日」のようなリピーター需要を掘り起こし6000万人突破も現実味を帯びますが、その場合長期滞在者が増えなければ消費15兆円は達成困難との指摘もあります。
交通インフラ整備: 観光客受け入れには航空・交通インフラの拡充が必要です。空港では国際線枠の拡大が進み、羽田空港では2019年比で国際線発着枠を32.2%増やすなど受け入れ能力を高めています。LCC(格安航空会社)の地方就航も進み、韓国など近隣国から地方都市への直行便が増加しました。ただし、地方空港への国際線就航は地元にビジネス需要等も併せ持たないと難しく、依然として多くの観光客は東京・大阪などハブ都市経由です。今後、大型イベントとして2025年大阪万博や、2030年に向けて大阪にIR(統合型リゾート)開業計画もあり、これに合わせたクルーズ船受入れ拠点の整備拡充が求められます。また、都市内交通や多言語案内などソフト面のインフラも継続的な改善が必要です。
宿泊施設と民間企業の対応: 2019年までのインバウンド急増期には大都市圏でホテル不足が顕在化し、高稼働率が続きました。コロナ禍で一時需要が蒸発した後、多くの宿泊事業者は人員削減を強いられ、現在は需要回復に人手と客室供給が追いつかない地域もあります。民間企業はこの好機に向け、新規ホテル建設や旅館の改装、地方の古民家を活用した宿泊施設開業など動きを活発化させています。政府も全国35の国立公園への高級リゾートホテル誘致を掲げ、2031年までに各公園に少なくとも1軒の高級宿を整備する計画です。また、民泊(ホームシェア)の規制緩和も行われ、ピーク時の宿泊需要分散に寄与しています。こうした供給拡大策に加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)による効率化で少ない人員でも回せる運営体制を作ることが急務です(後述)。
地政学的リスクと安全保障: 国際情勢の変化もインバウンド観光に大きく影響します。アジア地域の緊張や外交関係の悪化による旅行需要減退は既に前例があります。例えば2019年には日韓関係の悪化で韓国人訪日者が前年から大幅減少し、一時は前年同月比▲48%(2019年8月)という落ち込みを記録しました。中国についても政治的要因で団体旅行禁止措置が取られたり、訪日意欲が左右されるリスクがあります。また感染症の世界的流行やテロ・戦争リスクも潜在的な脅威です。特に中国・韓国など特定国に依存した集客はリスク分散の観点で課題があり、マーケットの多角化が重要です。一方、オーバーツーリズム(過度な観光客集中)も国内的なリスクと言えます。京都では近年、宿泊費高騰や混雑で日本人客が敬遠する動きも見られ、地元住民の観光アレルギーが広がれば持続的発展に支障を来します。安全・安心で地域と共生する観光の実現が求められており、各自治体が観光客のマナー啓発や受入れ制限施策(富士山の入山者数制限)といった対策を進めています。
2. 世界の観光トレンドと日本の位置づけ
世界的な旅行需要の拡大: コロナ禍前の10年間で国際観光客数は約4倍に増加し、日本への訪日客も飛躍的に伸びました。背景には、世界全体で年間5~6%の安定成長を遂げていた旅行需要拡大があります。特に2010年代前半はアジア太平洋地域の伸びが著しかったものの、直近では欧米を含め世界中で海外旅行者数が増加傾向にあります。2019年には世界の海外渡航者数が約15億人に達し、2023年には約13億人まで回復(前年比+33%)しました。UNWTOは長期予測で2030年に18億人と見込んでいます。こうしたマクロトレンドとしての追い風は、日本のインバウンド拡大にもプラス材料です。もっとも、パンデミックの影響でアジアの回復は欧米より遅れましたが、2024年以降はアジアも急回復し世界全体の勢いも取り戻しています。
主要観光先としての日本の地位: 日本は近年、国際的な旅行先ランキングで存在感を高めています。コロナ前の2019年、訪日外客数は世界11位(約3188万人)まで増加していました。しかしトップのフランスは8900万人、スペイン8300万人と桁違いで、東アジアでは中国(約6600万人※香港含む)が多い状況でした。最新の2023年統計ではフランスが1億人と過去最高を記録し、スペインやアメリカも8500万人を超えています。一方、日本は2024年に約3687万人で過去最高を更新しましたが、6000万人を達成できればイタリアやトルコ並みで世界5〜6位に食い込む規模となります。日本の旅行魅力度は国際的評価も高く、世界経済フォーラムの観光開発競争力指数では米国・スペインに次ぐ世界3位にランクされています。豊富な文化資源や良質なインフラが評価され、ポストコロナの訪問先として引き続き選好されるポジションにあります。ただし周遊性(他国と組み合わせた旅行)では欧州に劣るため、単独目的地として何度も訪れたくなるリピーター創出が課題です。

3. 今後訪日客が急増する可能性のある国・地域と背景
中国本土: 中国はコロナ前まで訪日客数・消費額とも最大のマーケットでした。2019年に約959万人が訪日し全体の3割を占めていましたが、ゼロコロナ政策の影響で2020~2022年は激減しました。2023年以降、中国政府が海外団体旅行を解禁し個人旅行も再開され、2024年の中国人訪日客は約698万人と前年比+187.9%の急増を見せています。依然2019年比では回復途上(約7割水準)ですが、潜在需要は極めて大きく、2030年にかけて中国からの訪日者数が再び1000万人規模に達する可能性があります。背景には中国の中間所得層の拡大と、円安による購買意欲の高まりがあります。中国人観光客は一人当たり消費額も高く、2024年には総消費額で国別トップとなり、アメリカや台湾を上回りました。今後、訪日ビザのさらなる緩和や航空路線の復便が進めば、一段の増加が期待できます。ただし政治的要因による旅行制限リスクは常につきまとうため、中国市場頼みとならない戦略的対応(富裕層・個人客へのシフトなど)が必要です。
東南アジア諸国: ASEAN諸国は経済成長と人口増によりアウトバウンド旅行者が急増しています。例えばタイは2010年代に訪日客が年2割前後のペースで伸び、2019年に約133万人に達しました。インドネシアやフィリピン、ベトナムも2019年時点で各40~50万人規模でしたが、潜在需要はさらに大きいとみられます。実際、2023年の訪日客数はフィリピン・ベトナムがコロナ前を上回る水準に回復し、インドネシアも急増しています。背景にはLCC路線の拡充や訪日ビザ免除(タイ・マレーシア・インドネシア※)の効果、そして日本文化(ポップカルチャーや和食)への親しみがあります。東南アジアからの旅行者は家族旅行やハネムーン需要も旺盛で、地方のスキー場や温泉に団体で訪れるケースも増えています。特にムスリム圏であるインドネシアやマレーシアでは、ハラール対応の飲食店や礼拝スペース整備など受け入れ態勢強化が奏功しつつあります。これら東南アジア各国は今後も安定した増加が見込まれ、日本政府も重点市場としてプロモーションを強化しています。
インド: インドは人口約14億人で2023年に中国を抜き世界1位となり、経済成長率も高水準が続く巨大な潜在市場です。インド人の海外旅行者数は過去10年で2.4倍に増え、2019年には約2,691万人が海外渡航しました。訪日インド人も2019年に過去最多17.6万人を記録し、コロナ後の2023年にも16.6万人まで回復しています。注目すべきはその消費額で、2019年274億円から2023年384億円へと1人当たり支出が大幅増加しています。インドでは中間層の所得向上と航空路線拡大(直行便はデリー・ムンバイ発着あり)が進み、今後も訪日者が増え続ける見通しです。日本総研の試算によれば、2030年代後半にはインドからの訪日客数が年間約100万人に達し、当時のタイからの訪日客数を上回る規模になる可能性があります。これはインドの人口動態(若年層が多い)と所得水準向上により、海外旅行に出る層が飛躍的に拡大するためです。インド人旅行者は桜や富士山、京都寺社など日本文化への関心が高く、今後はビザの緩和(2023年に短期観光電子ビザ開始)や菜食主義者への食対応強化などで受け入れを促進すれば、大幅な増加が期待できます。
欧米豪(欧米諸国・オーストラリア): 欧米豪からの訪日客も堅調に伸びています。2019年には米国から約175万人、欧州からは英国約40万人・フランス30万人・ドイツ20万人など合計で数百万人が訪日しました。コロナ後は円安の魅力もあり、特にアメリカ・オーストラリアからの旅行者が増えています。例えば2023年の米国人訪日者数はコロナ前比でほぼ回復し、富裕層による長期滞在やリモートワークを兼ねた滞在も見られます。また欧米からの旅行者は一人当たり消費額が高い傾向があり、高級旅館やミシュラン星付きレストラン、プライベートツアーなどへの支出意欲が強い層が含まれます。課題は距離の遠さによる航空運賃や所要時間ですが、直行便ネットワークの拡充や乗継利便性向上によりハードルは下がりつつあります。欧米市場は全体シェアは大きくないものの、長期滞在による地方周遊やオフシーズン訪問が多く、量より質でインバウンド需要を下支えする重要市場です。特に豪州はスキーやサーフィン等スポーツ目的のリピーターが多く、季節の反転を活かした通年誘客が期待できます。
中東・富裕層市場: 人口規模こそ小さいものの、中東湾岸諸国や香港・シンガポールなど富裕層市場も注目されます。中東からは近年エミレーツ航空などの増便で富裕な観光客が増加し、高級ブランド品購入や医療観光(人間ドック等)目的の需要もあります。また香港・シンガポール・台湾などは一人当たり所得が高く、リピーター率も高い市場です。こうした富裕層マーケットは訪日客数6000万人の「数」には大きな寄与をしない一方で、消費額15兆円の達成には欠かせない存在です。国・地域ごとに異なるニーズに合わせ、ラグジュアリー旅行商品の造成やVIP対応の充実を図ることで、更なる消費拡大が見込めるでしょう。

4. 6000万人の観光客を受け入れるための条件
宿泊施設の供給拡充と品質向上
6000万人規模の旅行者を受け入れるには、宿泊キャパシティの大幅な拡充が必要です。現在すでに訪日客の半数近くが東京に集中し、次いで大阪、京都、千葉(成田空港・東京ディズニー)と限られたエリアへの偏在が顕著です。2023年時点で東京を訪れる訪日客は全体の約48.6%、大阪43.5%と主要都市圏に集中し、地方への宿泊需要は低い水準です。大都市ではホテル開発が進んできたものの、6000万人ともなれば東京・大阪だけでは捌ききれず、地方都市や観光地での宿泊インフラ整備が不可欠です。
各地でホテル・旅館の新設や増改築を促進するため、政府は税制優遇や補助金で後押ししています。特に不足が叫ばれるのは中価格帯の宿泊施設で、団体客が泊まれる大型ホテルから個人旅行者向けのホステル・ゲストハウスまで幅広いタイプの供給が求められます。また、既存の老舗旅館などのリノベーション支援により質的向上も図っています。宿泊施設の供給量だけでなく質の向上も重要で、海外富裕層を呼び込む高級リゾートからバックパッカー向けまで、多様な需要に対応した宿泊ネットワークを全国で構築することが目標です。
地方誘客の進展と観光コンテンツの充実
観光客6000万人時代に備え、訪日客の地方分散は避けて通れない課題です。現状では外国人延べ宿泊者数の伸び率は、都市圏が2019年比+40.6%と急増する一方で地方部は+5.9%に留まり、都市と地方の格差が鮮明です。受け入れ余力のある地方にいかに旅行者を誘導するかが、観光立国の成否を握ります。政府は観光庁を中心に「地方誘客」の戦略を打ち出し、(1) 高付加価値な体験の提供と (2) 交通・情報面のハードル低減に取り組んでいます。
具体的には、地域ならではの自然・文化資源を活かした体験型観光の開発を支援しています。例として、長野や北海道でのアドベンチャーツーリズム(登山・サイクリング等)や、新潟や鹿児島でのガストロノミーツーリズム(郷土料理体験)を推進しています。また全国各地でナイトタイムエコノミー(夜間観光)や伝統祭りの国際PRなど、地域特有の魅力を磨き上げる取組みが広がっています。こうしたコンテンツ整備は時間がかかるものの、観光客を地方へ呼び込み「お金を落としてもらう」ためには不可欠です。
同時に、地方への移動を便利にする施策も重要です。LCCや地方路線の拡充、広域観光周遊パスの発売、多言語カーナビの普及などにより、外国人が地方を個人旅行しやすい環境づくりを進めています。自治体間連携で広域ルート(ゴールデンルート以外の新ルート)を提案し、周遊性を高める工夫もなされています。例えば北陸新幹線や九州新幹線沿線を巡るモデルコースの提案、クルーズ船で地方港に寄港させる誘致などです。「分散と充実」を両輪として、都市部への過度な集中を緩和しつつ地方経済への波及効果を高めることが6000万人達成の前提条件となります。
拡大後の人手不足対策と生産性向上
旅行者数の急増に対応するには、観光産業の人手不足問題を解決しなければなりません。調査によれば、もし6000万人を受け入れた場合、宿泊・飲食業で約53.6万人もの労働力不足が生じる可能性があると警告されています。日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少が続いており、人手不足は構造的な問題です。特にコロナ禍で人員流出した宿泊・飲食業では、まずは雇用をコロナ前水準に戻すことすら困難で、さらに6000万人対応のため増員するのは容易ではありません。人材確保なくしてサービス低下は避けられず、観光客満足度の低下→将来需要の喪失にも繋がりかねません。
この人手問題への対策として、多角的なアプローチが必要です。第一に、賃上げや処遇改善によって業界の魅力を高め、人材を呼び戻すこと。観光業の収益を人件費に再投資し、人材定着を図ることが産業強化に繋がります。第二に、海外からの労働力活用です。既にホテルや飲食で技能実習生・特定技能ビザの外国人が働き始めていますが、制度を柔軟に運用し、言語研修などサポート体制を整えることで戦力化を進めます。第三に、高齢者や主婦など国内の潜在労働力の活用や、副業・ボランティアによる観光支援(観光ガイドや通訳案内士など)の推進も有効でしょう。
根本的には生産性向上によって「少ない人でも回せるしくみ」を作ることが肝要です。これは次項のDX推進にも直結します。
宿泊施設運営の効率化(DX・スマートチェックイン等)
人手不足を補完しサービスの質を維持するため、観光業へのデジタル技術導入が急務です。例えばホテルではモバイルチェックインや顔認証によるスマートチェックインを導入し、フロント業務の省力化が進んでいます。また多言語翻訳アプリやAIチャットボットを活用したコンシェルジュサービスで、言語の壁を低コストでカバーする試みも広がっています。観光産業全体でIoTやAIを活用し、個々のニーズに合ったサービス提供を効率的に行うことが求められます。しかし中小の旅館・施設ではDXの進捗が遅れがちで、先進企業との格差が課題です。国や専門家が主導して業界全体の底上げ(デジタル人材育成・設備投資支援)を図ることが重要でしょう。
一方、ロボットや自動化技術の活用も進んでいます。客室清掃ロボットや配膳ロボットの導入により省人化とサービス継続を両立する例も出てきました。実際、観光業界では毎年2.8%程度の生産性向上が必要と試算されており、業務プロセスの見直し・デジタル化でこのギャップを埋める努力が求められています。DX推進により人手不足による対応力低下を補い、質の高い体験を持続的に提供できる体制を整えることが、6000万人受け入れの前提条件となります。
5. 観光消費額15兆円超えのための戦略
6000万人の誘致と並行して、一人当たり消費額を引き上げ総消費15兆円を達成する戦略も不可欠です。量だけでなく質(単価)を追求しなければ、仮に人数目標を達成しても消費15兆円には届かない恐れがあります。そこで政府は「観光の高付加価値化」を掲げ、以下のような施策で訪日客の支出増を図っています。
富裕層誘致と長期滞在の促進
一人当たり消費が大きい富裕層観光客の取り込みは、15兆円目標の達成に直結します。世界的に富裕層はユニークでプライベート感のある体験を求めるため、専用ガイド付きツアーや貸切施設、高級旅館での特別プランなどを充実させています。日本政府も国立公園におけるラグジュアリーリゾート誘致や、高級旅館の改築支援を行い、富裕層が満足できる受け皿づくりを推進中です。また、中東や欧米の著名人を招いたFamツアーで日本の高級観光をPRする施策も取られています。
加えて、長期滞在旅行者の増加も消費拡大に有効です。長期滞在者は宿泊・飲食に加え地域での生活消費(買い物や日常サービス利用)が増えるため、一人当たり支出が高くなります。欧米豪からの旅行者やデジタルノマド(リモートワーカー)向けに、最長1年滞在可能な特別ビザの検討や、ワーケーション受け入れ環境整備(高速WiFi完備の宿泊施設など)も議論されています。実際「消費額の増加には長期滞在が必要」との指摘もあり、リピーターが日本各地にゆっくり滞在できる仕組みづくりが肝要です。
地方での消費拡大策(体験・買物の充実)
消費15兆円の達成には、地方でどれだけ消費を生み出せるかがポイントになります。都市部(東京・大阪など)だけでなく地方でお金を使ってもらうには、その土地ならではの魅力ある商品・体験を提供する必要があります。現在、訪日客の消費内訳を見ると買物代が大きな比重を占めますが、購買品は都市の家電量販店や百貨店に集中しがちです。これを地方にも広げるため、各地の伝統工芸品や地場産品を訴求し、免税対応店舗の地方展開を支援しています。また地方の観光地で体験プログラム(農漁業体験、伝統芸能鑑賞、着物レンタル等)を用意し、それに参加してもらうことで体験料収入と関連消費(お土産購入や飲食)を増やす狙いです。
特に文化体験や食体験は地方消費拡大の目玉となりえます。茶道や生け花、日本舞踊といった伝統文化の体験教室、地元の祭りに参加できるツアー、酒蔵巡りや味噌作り体験など、訪日客が「ここでしかできない」体験に喜んで支出するコンテンツを創出します。例えば、富裕層向けに能楽師から直接指導を受けるワークショップや、ミシュラン星シェフと行く市場巡りなど高額でも満足度の高いプログラムが企画されています。これらは地方の伝統産業の維持にも繋がり、地域経済への波及効果が大きい取り組みです。
さらに滞在中の移動消費(交通費)を地方にも落とす工夫として、JRの周遊パスに地域クーポンを付与したり、レンタカー利用促進でガソリンスタンドや道の駅での消費誘導も検討されています。観光客5人分の消費が住民1人分の年間消費に相当するとも言われ、その恩恵を全国津々浦々に行き渡らせることが地方創生の観点からも重要です。
高付加価値旅行商品の開発と単価引き上げ
旅行消費額を増やすには、訪日客により高い価値に対してお金を払ってもらうことが必要です。政府の戦略でいう「観光の高付加価値化」に該当し、高価格でも満足度の高い商品・サービスを開発することに他なりません。具体例として、豪華寝台列車による周遊ツアーや、地域を深く知る専門ガイド付きテーマ旅(建築ツアー、アニメ聖地巡礼ツアー等)などが挙げられます。こうした特別感のある旅行商品は高単価ですが、熱心なファンには支持されています。
また、観光と他分野を掛け合わせた複合的な付加価値も重視されています。例えば医療や美容と組み合わせた医療ツーリズム(温泉+人間ドック、美容クリニック+観光)、教育旅行(日本語や和食を学ぶ長期滞在型ツアー)などです。農村民泊で日本の田舎暮らしを体験する滞在型観光や、企業経営者向けに禅寺でマインドフルネス体験をする研修プログラムなど、ユニークな付加価値旅行も登場しています。こうした取り組みは訪日客一人ひとりの滞在単価を底上げし、「人数頼みでない収益拡大」を可能にします。
観光産業側にも、価格設定戦略の見直しが求められます。これまで団体客誘致で安価に提供していたコンテンツも、需要に見合った適正価格に引き上げ、得られた収益をサービス向上に再投資する好循環を目指します。質に見合った対価を得ることは、結果としてスタッフの給与アップや設備改良につながり、さらなる高品質サービスの提供→満足度向上→口コミ拡大→新規需要創出というポジティブサイクルを生み出します。
おわりに:目標達成に向けた展望
以上の分析から、2030年までに訪日6000万人・消費15兆円を達成することは決して不可能ではないものの、極めて高いハードルであることがわかります。現在のペースからは年間9.4%もの成長を6年連続で続ける必要があり、供給体制強化と需要分散の両面で革新的な取り組みが不可欠です。単に数を追うだけではオーバーツーリズムや人手不足が深刻化し、将来的な持続性を損ねる恐れがあります。むしろ質と量のバランスを取り、観光客数の拡大と一人当たり消費の増加を両立させる戦略が求められます。
観光は日本経済にとって重要な成長エンジンであり、少子高齢化に直面する日本が外需を取り込む絶好の機会です。世界的な旅行需要の追い風を捉えつつ、日本ならではの魅力を磨き上げ、観光先進国にふさわしい受け入れ体制を築くことができれば、6000万人・15兆円という目標も視野に入るでしょう。その際、地域社会との共生や環境への配慮、そして何より訪れる人々の満足度向上を忘れずに進めることが肝心です。観光立国実現への挑戦は続きますが、質の高い観光による経済活性化と国際交流の深化に向け、官民一体となった取り組みが期待されます。